出産準備リストの中に「スワドル(おくるみ)」と書いてあるのを見て、正直「本当に必要なのかな?」と思っていました。
でも、生後すぐの赤ちゃんは夜中にモロー反射で何度もビクッと起きてしまい、私も寝不足でフラフラ…。
そんな時、先輩ママから「スワドルを試してみるといいよ」とすすめられ、半信半疑で使ってみました。すると――その夜はなんと3時間以上連続で眠ってくれたんです。まさに救世主!
でも同時に、「いつまで巻いていいの?」「寝返りをし始めたら危ないって聞いたけど、やめ時はいつ?」という新たな悩みも出てきました。
この記事では、私自身の体験を交えながら スワドルをいつからいつまで使えるのか、卒業のサインや移行の工夫 をわかりやすくまとめていきます。
スワドルを使い始めたきっかけ(生後すぐ〜1か月)
わが家でスワドルを本格的に使い始めたのは、生後2週間を過ぎたころでした。
昼間はよく寝るのに、夜になるとモロー反射でビクッと起きて泣いてしまい、そのたびに抱っこで寝かしつけ…。気づけば私は一晩で3時間も眠れていませんでした。
そんな時、育児本やSNSで「スワドルを巻くと赤ちゃんが安心して眠れる」と知り、思い切って購入。
最初に巻いたときは、正直「窮屈そうに見えて大丈夫かな?」と不安でした。
ところが、その夜は違いました。
いつもなら30分で起きていたのに、気づけば3時間以上もぐっすり。
「これがスワドル効果か!」と、心から驚いたのを覚えています。
さらに続けて使ううちに、寝かしつけルーティンの一部になり、スワドルを巻くと自然に眠る合図になるように。
新生児期の不安定な睡眠を乗り越える大きな助けになりました。
いつまで使える?実際の卒業サイン(2〜4か月ごろ)
スワドルに助けられていた日々も、赤ちゃんの成長とともに少しずつ変化が訪れました。
生後2か月半ごろになると、巻いても自分の腕をグイグイ出したがるように。寝かしつけ中に暴れて泣くことも増え、「あれ?そろそろ卒業のサインかな」と感じ始めました。
そして生後3か月に入ると、日中にゴロンと体をひねって寝返りしそうな動きを見せるように。
「寝返りを打てるようになると、スワドルのままでは窒息の危険がある」という小児科のアドバイスも思い出し、思い切って卒業を決意しました。
ただ、いきなりスワドルをやめた最初の夜は大失敗…。
安心できずに泣き続けて、私も赤ちゃんも眠れない状態に。
そこで次の日からは 「腕だけ出せるスワドル」 を使って段階的に慣らしました。腕を自由にできるようになったことで、赤ちゃんも徐々に安心して眠れるように。
最終的にはスワドルを完全に卒業し、スリーパーに切り替えました。
初めてスワドルなしでぐっすり眠れた夜は、「赤ちゃんも成長したんだな」とうれしい気持ちと少し寂しい気持ちが入り混じりました。
スワドル卒業後の工夫と代替グッズ
スワドルを卒業してからしばらくは、赤ちゃんが落ち着いて眠れるように色々と工夫をしました。
最初に取り入れたのが 「スリーパー」。掛け布団を使うのは窒息のリスクがあるため、小児科からも「布団の代わりにスリーパーがおすすめ」とアドバイスを受けていました。
我が家で選んだのは、季節に合わせて素材が選べるタイプ。
夏はガーゼ素材、冬はフリース素材で、寝冷えを防ぎながらも安全に使えるので重宝しました。
また、スワドルからの移行をスムーズにするために使ったのが 「腕だけ出せるスワドル」。
これは赤ちゃんが手を自由に動かせるので、寝返りしても安心。完全にやめる前の「つなぎ」として役立ちました。
さらに、寝る前のルーティンも意識。
「お風呂 → 授乳 → スリーパーを着せる → 電気を暗くする」という流れを毎日続けることで、赤ちゃん自身も「これから寝る時間なんだ」と自然に理解してくれるようになりました。
スワドルがなくても眠れるようになった今振り返ると、「卒業=赤ちゃんが一歩成長した証」なんだと感じています。
まとめ
スワドルは、新生児期の赤ちゃんにとって安心して眠れる大切なアイテムです。
私自身も、寝不足で限界だったときにスワドルに救われました。
ただし、使える期間は限られていて、目安は 生後3〜4か月ごろ、寝返りを始める前まで。
「腕を出したがる」「巻くと嫌がる」「寝返りの予兆がある」といったサインが見えたら、卒業のタイミングです。
卒業後は、スリーパーや腕抜きタイプのスワドルを取り入れたり、寝かしつけルーティンを整えたりすることで、赤ちゃんも自然に次のステップへ移行できます。
スワドルをやめるのは少し寂しい気もしますが、それは赤ちゃんが成長している証拠。
「もうスワドルに頼らなくても眠れるんだね」と前向きに受け止めることで、ママ・パパ自身も安心できますよ。
↑口コミ情報をチェックしてみる
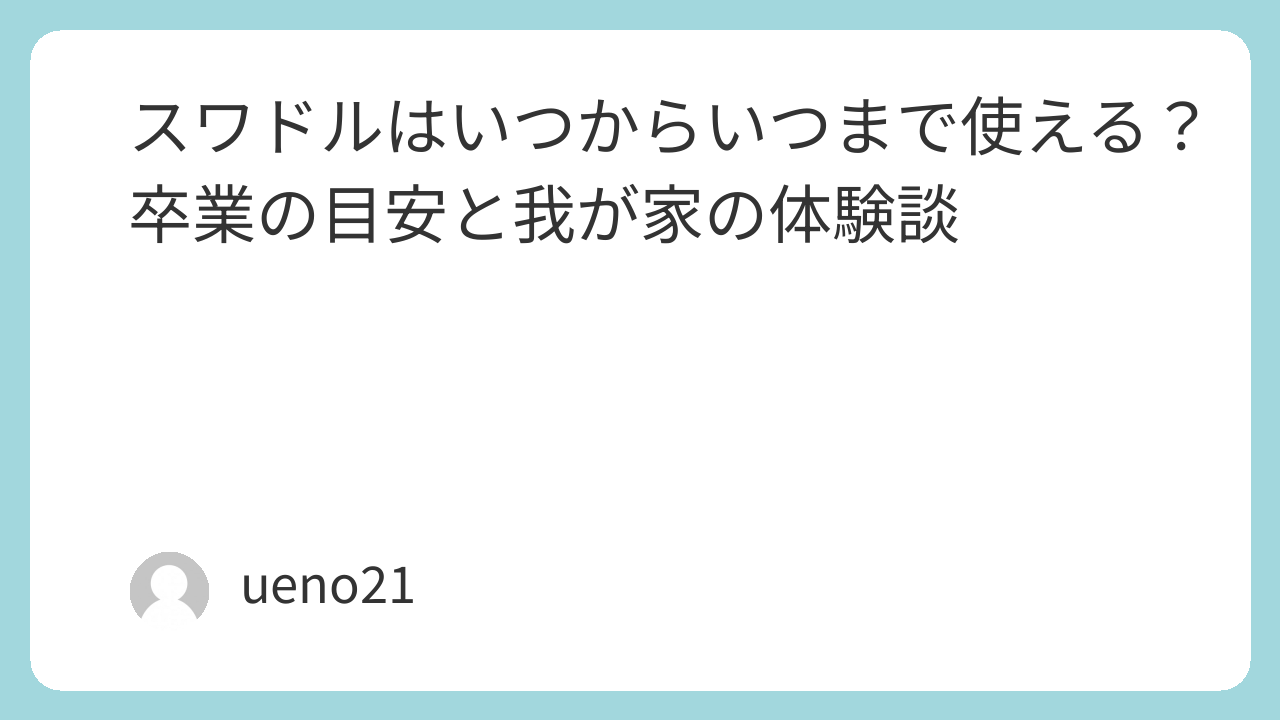


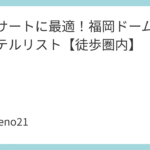
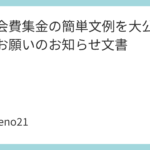
コメント